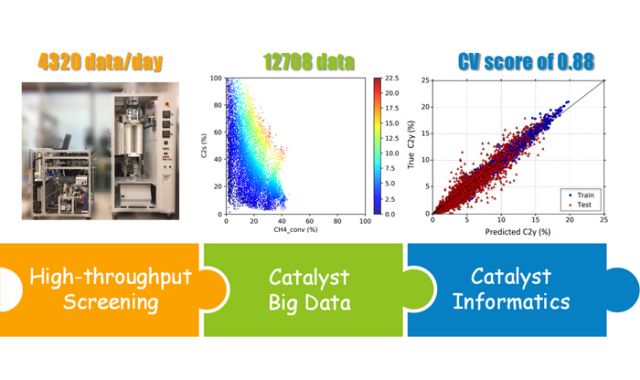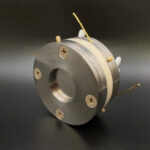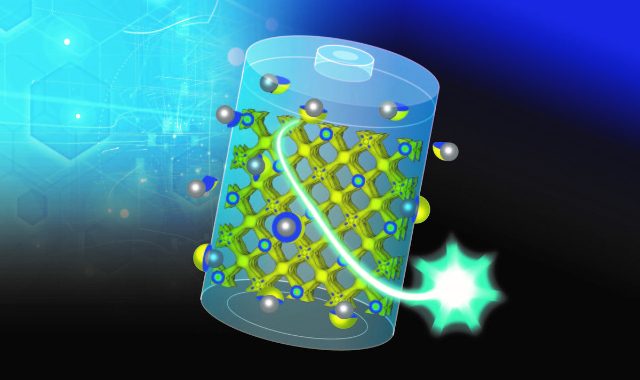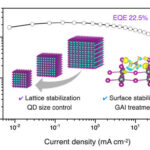- 2016-6-1
- エンジニアキャリア紹介, 制御・IT系, 機械, 電気・電子系
- BOCCO, iDoll, necomimi, Neurowear, コミュニケーションロボット, ユカイ工学, 青木俊介

中学生時代からパソコンが大好きだった

エンジニアである父親の影響が大きい。「手先が器用で、何でも作ったり、修理したり。自分もこうなりたいと思った」
――青木さんは、最初はソフトウエアのエンジニアだったそうですね。
中学生のころからパソコンが大好きで、当時からパソコンを触る仕事をしようと思っていました。いろいろな雑誌を買ってきては、付録のフロッピーディスクに入っているゲームで遊んだり、プログラムを作ってみたり……。インターネットが登場する前の時代ですが、飽きることはまったくありませんでしたね。
大学生のころ、インターネットブームが起き始めて、新しい世界にすごく興味を持ちました。自分もその世界で何かできるようになりたいと思ったので、大学に入学してすぐ、ホームページ制作のアルバイトを始め、仕事をしながらプログラミングを覚えました。
――大学生時代に会社も作られましたね。
友達と一緒に「チームラボ」という会社を作って、携帯電話アプリの開発などをしていました。当時はちょうどJavaが登場したころで、新しい技術がどんどん出てきている時代でした。使ってみなければ分からないので、常に自分たちで新しい技術を試しながら、それを使って企画をしたり、お客様に提案したり。私の場合は、仕事をしながら技術を身に付けていました。
「ロボットでやっていく」という決意表明

東大に加え、中国の大学も卒業。「結果的に中国語もある程度できるようになり、量産工場とのやり取りなどに役立っている」
――では、ハードウエアを扱うようになったきっかけは。
2005年ごろにアメリカで「MAKE」という雑誌が発売されました。アメリカに住んでいる知人が送ってくれたのですが、ハードウエアをDIYするような内容で、ハードの世界もすごく面白そうだなと思ったのがきっかけです。最初はキットを組み立てるようなことから、ハードの勉強を始めました。
ソフトウエアの世界では、インターネット初期からオープンソースソフトウエアが出始め、そのころにはWebサーバもデータベースも、アプリケーションサーバも、オープンソースが当たり前になっていました。ハードウエアの世界でも、同じようなことが起こるのではないか、通信モジュールやカメラモジュールといったコンポーネントを組み合わせて新しい物を作る世界になるのではないか、と感じました。
――ハードウエアの中でも、なぜ「ロボット」なのですか。
中学生のころから、一番やりたかったのはロボットを作ることでした。「ターミネーター2」という映画に登場する人工知能を作っているエンジニアに憧れて、こんな人になりたいとも思っていました。
2007年にチームラボを辞めてユカイ工学を立ち上げたのは、そろそろロボットでビジネスもあり得るのではないかと思ったから。「これからはロボットでやっていく」という、決意表明でもありました。