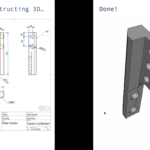- 2024-5-27
- 制御・IT系, 研究・技術紹介
- AutoML(Automated Machine Learning:自動化された機械学習), ChatGPT, FiNC, FiNCちゃん, Fitbit, PHR(パーソナルヘルスレコード), デジタルヘルスの推進, ヘルステック×AI, メンタルヘルスケア, 健康寿命, 坂井 俊介, 少子高齢化, 未病, 株式会社FiNC Technologies, 生成AI

株式会社FiNC Technologies 坂井 俊介氏
高齢化が急速に進展し、「人生100年時代」ともいわれる現代日本では、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」である健康寿命をいかに伸ばしていくのかが、重要な社会課題とされています。経済産業省が発表した「新しい健康社会の実現に向けた『アクションプラン2023』」では、方策の一つとして「デジタルヘルスの推進」が掲げられていますが、具体的にどのような取り組みが求められているのでしょうか。
今回の連載は「ヘルステック×AI」をテーマに全2回の構成とし、楽しく健康的な生活を実現するための予防医療に取り組む、株式会社FiNC TechnologiesのCTO 坂井 俊介氏にお話を伺いました。(執筆:後藤銀河 撮影:編集部)
<プロフィール>
株式会社FiNC Technologies
CTO プロダクト本部 技術開発部 部長 坂井 俊介氏
東京大学大学院情報理工学系研究科システム情報学専攻修了後、同社に入社。2020年からはtoC事業の開発チームのテックリードとして、チームビルディングや開発プロセス改善に従事。2022年より技術開発部の副部長に就任。ビジネス負債・技術的負債への感度が高く、内外の環境変化に適応的なプロダクト設計を得意とする。2023年5月にCTO就任。
深刻化する高齢社会、健康寿命の延伸は重要な社会課題
――ヘルステックの技術領域が成長している背景を教えてください。
[坂井氏]日本全体の大きな社会課題として、少子高齢化やそれに伴う社会保障費の増大があります。国も国民の健康寿命の延伸や、豊かで幸福な生活の実現を重要課題と捉え、個人の健康を重要視した政策を打ち出しています。こうした背景から、ヘルステックの領域で定期検査の義務化や残業規制の厳格化、メンタルヘルスケアなどに対応した新しいソリューションが次々と生まれるようになったのです。ヘルステックは市場規模もどんどん拡大している、期待の技術領域と言えるでしょう。
――御社はヘルステックの領域で、どのような事業を展開されているのでしょうか?
[坂井氏]弊社はコアバリューとして、「Design your Well-being:一人ひとりが、自分らしい豊かな生活を描ける世界に」を掲げ、私たちの事業やアプリに関わった人々が豊かな人生を送れることを目指しています。
事業モデルは大きく3つあり、まず「FiNC」アプリを中心としたBtoCビジネス。次に、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する健康経営が重要視されるようになりましたが、その健康経営を支援する法人向けのSaaSサービス。そして、弊社が持つ健康管理の基盤と、協業する企業のアセットを組み合わせたDXビジネスを展開しています。これらの中から、「FiNC」アプリを紹介させていただきます。
「未病」にフォーカスし、生活習慣や行動の改善をサポートするサービスを提供
[坂井氏]一般的にヘルステックとは医療行為を含む広い領域を指しますが、私たちは健康な人がまだ病気になっていない「未病」の状態にフォーカスし、スマートフォン向けアプリ「FiNC」を中心としたサービスを展開しています。未病の方には、「健康状態に不安があるが、どうしたら良いのかわからない」「健康になれる方法がわかっていても実行に移せない」「健康行動が継続できない」などの悩みがあります。このような悩みに対し、生活習慣や行動を改善するソリューションを提供しているのです。
FiNCアプリには健康意識の高い方から低い方まで様々なユーザーがいます。健康意識が高めのユーザーは、アプリからアドバイスを受けてそれを実行し、結果を確かめることが重要になりますが、健康意識が低めの方にとっては、生活習慣や行動改善を自力で行うのは結構難しいことなのです。そこで私たちも様々な工夫を凝らし、ユーザーの行動喚起を促しています。
例えば、ユーザーが手動でデータを入力する必要がないように、「Fitbit」など他のデバイスと連動して自動でデータを取り込めるようにしています。他にも、ただデータを取得しているだけでは人によってはあまり面白みがなく、続かなくなってしまうこともあります。そこで歩いて達成することでポイントが貯まったり、ガチャが引けたり、ユーザーに対するインセンティブになるような、アプリを使うことが楽しくなる仕組みも導入しています。こうした仕組みもWell-beingという視点からは、大切なことだと考えています。
アプリで取得するライフログデータをビジネスに活用できるデータ基盤へ
――ヘルステックに注目が集まる中、様々なアプリがリリースされていますが、「FiNC」の強みはどこにあるのでしょうか?
[坂井氏]ヘルステックの健康管理という大きな枠組みの中で考えると、歩数、食事、運動、体重、睡眠管理など、単機能に特化したアプリはたくさんありますが、FiNCはこうした多角的なデータが全て取得できるということ、そして一つのアプリで健康管理の全方面を網羅したサービスが提供できることが強みだと考えています。
FiNCは2017年3月のサービス開始以来、累計1,200万を超えるダウンロードがあり、ユーザーのライフログデータ(歩数、食事、運動、体重、睡眠、生理など)が145億以上(2023年3月時点)蓄積されています。これが様々なビジネスに活用できるデータ基盤となり、これは弊社のBtoBソリューションに活用する他にも、企業や自治体が持つアセットと組み合わせて健康管理機能をビルドインした多様なアプリの提供を可能にしています。
私たちがFiNCを通して蓄積しているライフログデータは、健康に関連するデータで日々変化します。ヘルステックのニーズとして、健康状態が悪化するリスクを想定したり、健康診断の結果から予測したりするサービスが強く求められるようになっています。FiNCのコアコンピテンシーはライフログデータ基盤だと言いましたが、より精度の高い予測のためには、より多くのデータを蓄積しながら他の企業と協業することが必要です。そうすれば、健康診断データやレセプトデータをはじめとした別チャネルのデータと組み合わせ、より優れたソリューションが生まれるのではないかと考えています。

FiNCアプリは、歩数、食事、運動、睡眠など様々な情報を一つのアプリで管理できる
ユーザーの入力支援や自然なインタラクションがAIの強み
――次はAIの活用についてお聞きします。御社では、どのようなところにAIを活用されているのでしょうか。
[坂井氏]代表的な活用方法としては画像解析があります。例えば、FiNCアプリでユーザーの食事記録をする際に、食事の写真をスマホで撮影し、それをAIで画像解析することで、味噌汁、ご飯、野菜などを判別し、ユーザーが手入力する手間を省くためにメニューを自動解析できるようにしています。
他にも分析系の機能になりますが、睡眠記録を自分で毎日取得するのは大変なので、例えばFiNCアプリと連携させているウェアラブルデバイスの動きなどから、ユーザーのアクティブ時間を推定し、いつからいつまでが睡眠時間だったという分析に、AIを活用しています。
あとは、今話題の生成AIですね。ChatGPTに刺激される形で、2023年以降、AI分野では大手からスタートアップまで開発競争が激化しています。AI全体の技術トレンドとしては、この生成AIの他に、AutoML(Automated Machine Learning:自動化された機械学習)などが注目されています。
AutoMLの領域では、ある程度のデータが集まればモデルを自動的に生成してくれるようなサービスプロバイダーが出てきているので、アルゴリズムの調整や精度といった技術的な差異はなくなってきていると感じます。そうした領域は、AmazonやGoogleなどその技術に特化したソリューションを提供する一部の企業に任せ、私たちは特徴量をどう設計するか、といった領域に注力すべきだと思います。
また、ライフログデータ、PHR(パーソナルヘルスレコード)を価値あるデータ基盤として構築するためには、ユーザーが取得するデータの質をいかに担保するかが非常に重要です。データを忘れず正しく入力してもらうためには、ユーザーに対してきちんと伝えられるよう、やり取りのインターフェースを設計する重要性が高まってくると思います。

――生成AIはIT大手も巻き込む形で選択肢が増えてきました。身の回りで実際に利用しているという声も聞きますが、FiNCでは生成AIをどのように評価されていますか?
[坂井氏]生成AIの強みは、やはり自然言語でのインタラクションができるところですね。例えばFiNCアプリには「FiNCちゃん」というキャラクターがいて、ユーザーの行動に対してメッセージをプッシュしたり、有用な情報を提供したり、ユーザーがアプリを使っていく中で「楽しいな」と感じられるような、インタラクションを促進する存在がいます。こうした領域で生成AIが効果的に利用できると思っています。
ただ、生成AIが自動的にソリューションを生み出したり、ユーザーへのアドバイスを自動生成したりする機能の実現は、まだまだ難しいのではないでしょうか。ハルシネーション(注:AIが学習したデータからは正当化できないような回答をしてしまう現象)の問題もありますので、予防医療から医療領域までサービスを展開するとなったら、いい加減なアドバイスをユーザーにしてしまうことは絶対にできません。
まだまだ生成AI単独でサービスが成り立つまでには至っていないので、最終的にエビデンスをしっかり確かめた上でのアドバイスや、データの裏付けのあるソリューション、それが提供できる知見を持っていることが、ヘルステック領域でサービスを提供する際の強みになるだろうと考えています。
次回は、「医療×ITで進めるヘルステック戦略とは」と題してお話を伺います。
取材協力

ライタープロフィール
後藤 銀河
アメショーの銀河(♂)をこよなく愛すライター兼編集者。エンジニアのバックグラウンドを生かし、国内外のニュース記事を中心に誰が読んでもわかりやすい文章を書けるよう、日々奮闘中。