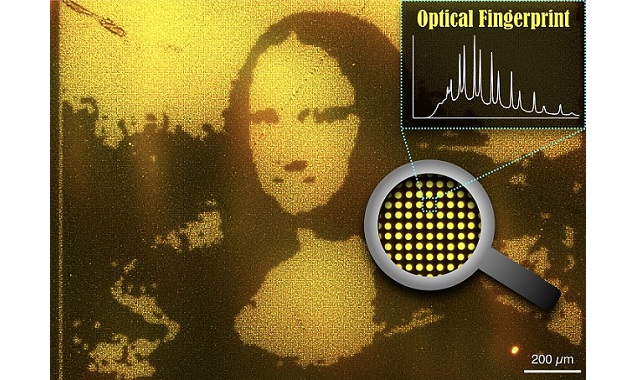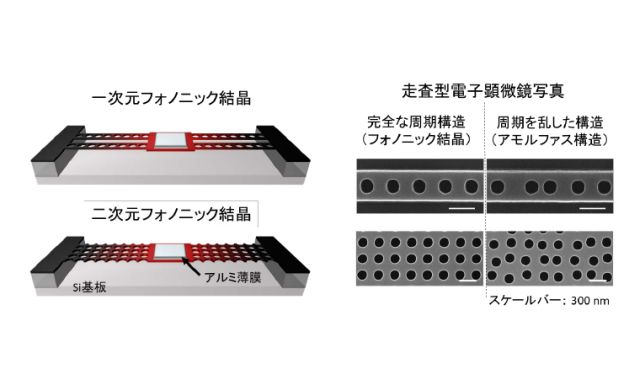- 2024-5-27
- REPORT, 制御・IT系, 化学・素材系, 機械系, 電気・電子系
- 3Dプリンター, CFRP, ChatGPT, GFRP, VisualSLAM, エナジーハーベスト, ディジタル信号, データ分析, ドライエッチング, プラスチック加工, マテリアルズインフォマティクス, モータ, ラマン分光法, 半導体, 半導体パッケージ, 図面, 拡散接合, 樹脂材料, 機械装置, 流体力学, 潤滑グリース, 環境発電, 生成AI, 電動化, 電動車, 電解加工

エンジニアの皆さんのお仕事、キャリア形成に役立つ、展示会・見本市、セミナー情報を毎週お届けします。
※掲載している展示会・見本市、セミナーの情報は、5/27時点のものとなります。申し込み状況は各サイトにてご確認頂けますようお願い致します。
目次
展示会情報(会場別)
- ワイヤレスジャパン 2024×ワイヤレス・テクノロジー・パーク(WTP) 2024【関東】(東京ビッグサイト)
- JECA FAIR 2024 ~第72回電設工業展~【関東】(東京ビッグサイト)
- 関西ロボットワールド2024【関西】(インテックス大阪)
セミナー情報
<機械系>
- 機械装置の疲労破壊を防ぐ方法
- 流体力学の基礎と応用
- 「ねじ・ボルト」のゆるみを防止する技術
- プラスチック加工の基礎と成形不良対策を学ぶ
- 騒音・振動低減基本技術とそのための材料の適用法
- 拡散接合の基礎・最新技術動向と接合部評価の実際
- 3Dプリンタの最新技術動向と樹脂材料開発における今後の展望
- 潤滑グリースの基礎と応用
- 熱硬化性樹脂複合材料 (GFRP&CFRP)の基礎とリサイクル技術
- 加工方法の性質を考慮した意義ある図面の書き方と活用法
<電気・電子系>
- 電解加工技術の基礎と応用技術
- ディジタル信号処理による雑音・ノイズの低減/除去技術とその応用
- 電磁波および電磁波ノイズを活用したエナジーハーベスト(環境発電)の技術動向と情報通信技術への応用、実用化への課題および展望
- EV用モータの技術トレンド
- <カーボンニュートラルへ電動化のコア技術>電動化(EV駆動等)モータと回路基板の高電圧化・高周波化・熱対策に向けた、樹脂材料開発と絶縁品質評価技術
<制御・ソフト系>
<IT系>
<化学系>
<半導体系>
- “半日で習得!”半導体技術の全体像マスター講座
- 半導体パッケージ技術の基礎と課題解決およびFOWLP等の最新技術動向
- ドライエッチングのメカニズムと最先端技術
- 半導体製造におけるシリコンウェーハのクリーン化技術・洗浄技術
- 車載半導体の最新技術と今後の動向
<分野共通>
展示会情報
会場名 東京ビッグサイト
イベント名:ワイヤレスジャパン 2024×ワイヤレス・テクノロジー・パーク(WTP) 2024
会期:2024年5月29日(水)~5月31日(金)10:00~18:00 ※最終日は17:00終了
会場:東京ビッグサイト 西3/4ホール
入場料:詳細はサイト内でご確認ください。
主催者:リックテレコム
概要:「ワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パーク(WTP)」は、日本最大級の無線通信の専門展示会です。ワイヤレスジャパンの初開催は1996年、WTPは2006年。2013年から共同開催がスタートしました。
最先端のワイヤレス動向を長年にわたり紹介してきたワイヤレスジャパン×WTPには、今年も5G/ローカル5G、Wi-Fi 7、IoT無線、ミリ波/テラヘルツ波、ワイヤレス給電など、注目のテクノロジーとソリューションが集結します。
通信ネットワーク産業に関わる方はもちろんのこと、デジタル変革を推進中の方、新規ビジネス開発に携わる方など、最新テクノロジーに関心をお持ちのあらゆる方に役立つイベントです。
URL:https://www8.ric.co.jp/expo/wj/
イベント名:JECA FAIR 2024 ~第72回電設工業展~
会期:2024年5月29日(水)10:30~17:00、5月30日(木)10:00~17:00、5月31日 (金) 10:00~16:30
会場:東京ビッグサイト 東1/2/3ホール
入場料:詳細はサイト内でご確認ください。
主催者:日本電設工業協会
概要:本展示会は、電気設備に関する資機材、工具、計測器、ソフト、システム等の新製品紹介を始め、施工技術や施工実績、アカデミックの紹介、電気設備業界の魅力や働き方などを紹介する各種イベントなど、あらゆる情報を発信する国内最大の電気設備総合展示会です。
URL:https://www.jecafair.jp/
会場名 インテックス大阪
イベント名:関西ロボットワールド2024
会期:2024年5月30日(木)、31日(金)10:00~17:00
会場:インテックス大阪
入場料:詳細はサイト内でご確認ください。
主催者:関西ロボットワールド実行委員会(大阪国際経済振興センター、エグジビションオーガナイザーズ)
概要:急速に発達・発展する注目度の高いロボット・次世代モビリティ産業。本展はロボットや次世代モビリティの開発・導入を促進する専門技術展です。
URL:https://www.srobo.jp/
セミナー情報
機械系
セミナー名:機械装置の疲労破壊を防ぐ方法
開催日時:2024年5月28日(火)10:00~17:00
場所:ライブ配信
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:新技術開発センター
概要:疲労破壊は、機器や構造物の部材に対して荷重が繰返して応力が発生すると、その応力によってまず微小なき裂(ひび割れ)が発生し、やがてそれが繰返しごとに少しずつ成長(進展)を始め、最終的には部材の破断に至るという現象である。
この疲労破壊は、発生応力が耐力を越えた大きなレベルで発生すると、繰返しのたびに新たな塑性変形が発生し、繰返し回数がほぼ1万回以下で破断に至るが、発生応力が耐力以下(すなわち弾性応力)で発生する場合には、1万回を超えて破断に至る。前者のような現象を低サイクル疲労、後者を高サイクル疲労と呼んでいる。
このような疲労破壊を防止することは永遠の課題であり、 機械設計者はその現象の仕組みを理解したうえで、発生防止の対策を講じなければならない。
また、疲労破壊にはき裂(クラック)の発生がつきものであるが、き裂の強度評価を行う場合には、材料を強度ではなくて靭性(脆さ粘さ)という面から検討するための破壊力学の知識も必要となってくる。
このセミナーでは、設計者が疲労の仕組みを理解できるように、また破壊力学が理解できるように説明し、疲労破壊の防止対策が簡単に行えるように解説する。
URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/42369
セミナー名:流体力学の基礎と応用
開催日時:2024年5月28日(火)10:30~16:30
場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:R&D支援センター
概要:私たちは空気や水といった流体に囲まれて生きています。このため、その運動の理解はさまざまな分野で重要ですが、流体力学は「分かりにくい分野」でもあります。この講座では、流体力学の基礎を丁寧にかつポイントを押さえて説明したのち、流体の数値シミュレーション手法やその応用(攪拌など)事例、そして最新の機械学習の応用についても、分かりやすく解説します。
URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/240536
セミナー名:「ねじ・ボルト」のゆるみを防止する技術
開催日時:2024年5月28日(火)13:00~17:00
場所:ライブ配信
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:新技術開発センター
概要:本セミナーでは、建設機械・産業機械でのねじ締結体設計とトラブル対策に関して豊富な経験を持つ講師が、ねじ締結の基礎技術を解説するとともに、実務で即活用できるねじの強度評価技術(疲労寿命推定法)、ゆるみのメカニズムなどについても詳しく解説します。
また、講師の製品開発を通した実務経験で得たねじに関する参考図書・資料・テストピースを紹介します。さらに、問題解決力・実践力を身につけるための実践的な演習も行います。
URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/42366
セミナー名:プラスチック加工の基礎と成形不良対策を学ぶ
開催日時:2024年5月29日(水)10:00~16:00
場所:ライブ配信
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:新技術開発センター
概要:本セミナーでは、射出成形の専門家である講師が、成形不良という視点での射出成形技術の基礎知識、および全18パターンにおよぶ成形不良の原因と対策について詳しく解説します。
URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/42370
セミナー名:騒音・振動低減基本技術とそのための材料の適用法
開催日時:2024年5月30日(木)10:30~16:30
場所:【東京】江東区産業会館 第2会議室(東京都江東区東陽4-5-18)
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:R&D支援センター
概要:騒音・振動課題もいろいろな分野で取り上げられ、計画、設計段階から”低騒音”や”低振動”が取り組まれるようになってきている。そのためには、騒音や振動の低減技術を総合的に理解し、そのための防音、防振の代表的な材料を知り、いかに上手に適用するか実践的な視点からお話しする。
ここでは、騒音低減の立場から、固体伝搬音と空気伝搬音に分け、その低減技術の基本としての振動絶縁、制振、遮音、吸音メカニズムとそれらを達成するための材料の役割と機能を実践的な面から解説させていただく。同時にその効果的な適用法について、実際の材料を見ていただき、事例と簡単なデモを行いながら理解を深めていただきたいと考えている。また、その中で、最近の動向を予想して、現在私が取り組んでいる防音・防振材料と他分野で実績のある材料の防音防振分野への適用展開についてご紹介もさせていただく。
URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/240214
セミナー名:拡散接合の基礎・最新技術動向と接合部評価の実際
開催日時:2024年5月30日(木)10:30~16:30
場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:サイエンス&テクノロジー
概要:開発された高性能材料が接合加工できなくては、新たなハイテク製品を組み立てることができません。特に水素関連設備、半導体製造装置、パワー半導体の組み立てには、微細接合、精密接合、異種金属接合が必須であり、この接合法として材料を溶融することなく接合する拡散接合が重要となります。
本セミナーでは、固相接合における拡散接合の位置づけの紹介に始まり、拡散接合の動向(論文、適用例、研究者、企業)、拡散接合の適用例(現状、適用のポイント、時代的変化)、拡散接合装置、拡散接合の接合機構、接合改善策、接合のポイント等を説明します。拡散接合のみならず、固相接合部の特性を支配する金属学的因子、施工因子の観点からそのポイントの説明と、パワー半導体の接合法は、各種接合法の縮図であることを紹介する。また、実用化に際しての重要な接合部の評価法について、接合前・接合中での評価のポイントと接合後の機械的、金属学的、非破壊的(超音波、X線)等の適用例の現状を説明します。理解を深めるため、拡散接合を適用した実物の紹介の他、動画を交えて解説します。 また、個別的な質問にも対応します。
URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/st240513
セミナー名:3Dプリンタの最新技術動向と樹脂材料開発における今後の展望
開催日時:2024年5月30日(木)13:00~17:30
場所:ライブ配信
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:AndTech (&Tech)
概要:3Dプリンターを活用した付加製造技術(AM技術)は従来からの射出成形加工やプレス・切削加工などと同列の加工手法であるが、多くの特徴を有している。
本講演では加工方法としての特徴を説明するとともに、加工方法の特徴から生まれる技術的・製品的長所とそれに伴う企業活動視点からの長所も含めて把握してゆく。市場での導入事例や展示会での最新事例を示しながら3Dプリンティング技術が可能とする今後の新しいモノづくりの輪郭と、課題を含めた現状を認識できる形で解説してゆく。※ほか、計3部構成。
URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/44010
セミナー名:潤滑グリースの基礎と応用
開催日時:2024年5月31日(金)10:30~16:30
場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:R&D支援センター
概要:潤滑グリースは、高速回転性能、耐摩耗性などその性能は潤滑油と比べて劣ることが多い。しかし油タンク、循環装置、冷却装置、フィルターなどが無くても使用可能となるため、機械や設備の小型軽量化に適して、その使い勝手の容易さから転がり軸受や歯車では主流の潤滑剤・潤滑方法となっている。潤滑グリースの流動性能が、摩擦トルク、音響性能,寿命等を支配することが多いため、その選定や使用においては実績を重視しなければならない。
本講座では潤滑グリースについての基礎から応用まで詳細な解説を行う。受講生の方々が潤滑グリースについての知見や経験を増すことによって、潤滑グリースの開発や性能向上、その選定や使用が正しく行われ、機械や設備の性能向上に貢献できることを期待する。
URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/240519
セミナー名:熱硬化性樹脂複合材料 (GFRP&CFRP)の基礎とリサイクル技術
開催日時:2024年5月31日(金)10:30~16:30
場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:R&D支援センター
概要:熱硬化性樹脂複合材料の代表的な製品としては、不飽和ポリエステル樹脂/ガラス繊維複合材料(GFRP: Glass Fiber Reinforced Plastics)、エポキシ樹脂/炭素繊維複合材料(CFRP: Carbon Fiber Reinforced Plastics)が挙げられる。CFRPに使用される炭素繊維(CF)は高価なため、最近はリサイクルされ始め、回収CFの用途探索も進んできた。
一方、CFRP生産量の20倍以上生産されているGFRPについては、2000年頃から約20年間、セメントの原燃料化によるリサイクルしか実用化されていなかった。しかしながら、ここ数年でリサイクル技術は著しく進歩、GFRP製の風力発電用ブレードなどがリサイクルされるようになってきた。また、CFRPについてもリサイクル事業へ参入する企業が増え、様々な用途開発が行われている。本セミナーではGFRP並びにCFRPのリサイクル技術に関する最新動向を報告するとともに、これらの技術を理解するうえで必要なGFRP並びにCFRPに関する基礎知識を概説する。
URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/2405129
セミナー名:加工方法の性質を考慮した意義ある図面の書き方と活用法
開催日時:2024年5月31日(金)12:30~16:30
場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:R&D支援センター
概要:設計業務においては、3Dデータを利用した製品や金型の設計が主流になっています。一方で、皆さんの会社では二次元の図面を有効に活用できているでしょうか。手間と時間をかけて図面を作り上げても、設計者から見て完璧と思えたものが、製造する人や寸法を測定する人からすると不十分、不適切と言われることもあるのではないでしょうか。
製造者や品質管理者にとっても意義のある図面とするためには、選択した加工方法による加工品の性質を考慮し、幾何特性仕様(GPS)を意識して図面を書く必要があります。
しかし、実際には、加工品の性質を考慮していない図面や、ノギスで測れるような単純な形状のみを前提とした図面を見かけます。このような図面で生産した製品は、寸法等の精度評価が曖昧になり、図面の意義が失われる結果、不具合や事故の発生を予見できないといった問題を引き起こします。
そこで、加工方法ごとに適切な図面の書き方を詳しく解説するセミナーを開催いたします。本セミナーでは、設計者が意図する仕上がり精度を適切に図面に反映させるとともに、製造者や品質管理をする側にとっても意義のある図面の書き方をわかりやすく説明します。
URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/2405122
電気・電子系
セミナー名:電解加工技術の基礎と応用技術
開催日時:2024年5月28日(火)10:30~16:30
場所:ライブ配信(Zoom)
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:サイエンス&テクノロジー
概要: 本セミナーでは、電解加工技術の概要、特徴と応用を説明し、電気二重層、材料溶出メカニズム、溶出速度、平衡加工間隙等の電解加工の基礎を解説する。なお、同じく非接触の加工法で、金型の製作に多く利用される放電加工技術との相違や使い分けについて解説する。
URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/43664
セミナー名:ディジタル信号処理による雑音・ノイズの低減/除去技術とその応用
開催日時:2024年5月29日(水)10:00~16:30
場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:トリケップス
概要: 本セミナーでは、実環境での雑音の種類から話をスタートし、ディジタル信号処理において、それぞれの雑音に対して、どのような対処策があるかを詳細に説明します。具体的なアルゴリズムを提示し、結果を確認しながら解説しますが、雑音の性質に応じた各種フィルタリング技術から、時変性がある従来対処困難とされていた雑音に対しても有効に働く、フレーム内処理方法やディープニューラルネットワークの利用までをカバーします。最先端のWave-U-Netやその改善方法なども説明します。
応用例として、音と通信を特に取り上げますが、実応用はこれらに限定されるものではありません。本セミナーでは、講師のこれまでの複数の企業との共同研究の知見から、現場で遭遇する雑音対策のノウハウを様々な角度から紹介して、受講者の抱える雑音問題の最適な解を提供することを目指します。それぞれの状況に応じて、最適解は異なるものになると予想できます。
URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/tr240511
セミナー名:電磁波および電磁波ノイズを活用したエナジーハーベスト(環境発電)の技術動向と情報通信技術への応用、実用化への課題および展望
開催日時:2024年5月30日(木)10:30~15:10
場所:ライブ配信
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:AndTech (&Tech)
概要:京都大学 篠原氏、ソニーセミコンダクタソリューションズ 吉野氏、電気通信大学 村松氏が電磁波および電磁波ノイズを活用したエナジーハーベスト(環境発電)の技術動向と情報通信技術への応用、実用化への課題および展望~レクテナの設計、電磁波ノイズを活用するエナジーハーベスト・モジュール、生体と電磁波の相互作用~について解説する講座です。
URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/44045
セミナー名:EV用モータの技術トレンド
開催日時:2024年5月30日(木)10:30~16:30
場所:【東京】AP秋葉原 1F Oルーム(東京都台東区秋葉原1-1 秋葉原ビジネスセンター)、Webセミナー(Zoom)
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:S&T出版
概要:地球温暖化対策として世界的にエンジン車の販売禁止が検討され、近い将来、電動車のみが販売できるようになるように伝えられている。わが国でも同じような動向である。それに伴い、電動車の研究開発が活性化している。電動車のキーコンポーネントは、モーター、パワーコントロールユニット(PCU)、バッテリである。このうち、モーターの性能は車の性能に直接影響する。すなわち、モーターはすべての電動車のキー技術である。
そこで、本セミナーでは、電動車に使われるモーターについて、基本技術、性能、冷却、小型化、高速化等の技術を解説し、今後の動向を展望する。
また、最近よく聞かれるe-axleについても述べる。電動車に関連した研究開発に携わる技術者にとって一つの指針となるようなセミナーにすることを目標にしている。
URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/43244
セミナー名:<カーボンニュートラルへ電動化のコア技術>電動化(EV駆動等)モータと回路基板の高電圧化・高周波化・熱対策に向けた、樹脂材料開発と絶縁品質評価技術
開催日時:2024年5月31日(金)10:00~17:00
場所:ライブ配信(Zoom)
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:サイエンス&テクノロジー
概要:本セミナーでは、部分放電特性について十分理解し、EVのパワートレインの構成部品、駆動モーター本体とパワーモジュール、さらにそれらを電子制御するプリント基板回路において、「いかに絶縁トラブルにつながる部分放電を発生させないか!」の基本対策について基礎事項から学べるように初歩から応用まで詳しく解説する。また、自社開発の高機能な樹脂絶縁材料をEVモーターや半導体基板材料に適応する場合、その技術課題と特性評価方法について分かり易く解説する。
URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/43239
制御・ソフト系
セミナー名:1日で分かるVisualSLAMの基礎
開催日時:2024年6月3日(月)10:00~16:00
場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:トリケップス
概要:本セミナーでは、コンピュータービジョンの初学者から包括的に学びなおしたい方、上記技術に従事することになった方など対象に、3次元的な自己位置推定・マッピング処理を対象としたコンピュータービジョン技術を初歩から概説します。カメラの投影モデルや特徴点トラッキングなどの基礎技術から、古くから研究がなされてきたオフライン型structure from motion(SfM) 、Hololens、ARCore、ARKitなどにも用いられるオンライン型visual SLAMの枠組みに至るまでを理解できることを目的とします。
URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/tr240601
IT系
セミナー名:すぐ実践できる!データ分析・超入門
開催日時:2024年5月28日(火)13:00~16:00
場所:ライブ配信(Zoom)
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:新社会システム総合研究所
概要:本セミナーでは、ビジネス数学教育の第一人者である深沢真太郎講師をお迎えし、データ分析の「そもそも」から学び、明日から使える仕事術として身につけます。難しい理論や数式はまったく使わず、数字に苦手意識のある方でもすぐに実践できる内容に厳選。数値やデータにもっと強くなりたい方、初心者の方に向けた講座です。
URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/42667
化学系
セミナー名:CO2分離回収技術に関連したプロセスおよびコスト計算の基礎と実例
開催日時:2024年5月29日(水) 10:30~16:30
場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:R&D支援センター
概要:本セミナーでは、CO2分離回収技術を中心としてプロセス評価及びコスト検討方法の基礎について解説します。物質収支やエネルギー収支の計算方法の基礎、熱交換器の所要伝熱面積の計算、コンプレッサーの所要動力などを、Excelなどを用いた実際の計算例とともに解説します。さらに、CO2分離回収技術の選定やプロセス改良を行うための基礎となるコスト計算法の基礎について解説します。
URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/240582
セミナー名:ラマン分光法の基礎と分析事例
開催日時:2024年5月30日(木)13:00~15:30
場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:R&D支援センター
概要:ラマン分光法は、純粋な金属を除く無機物・有機物の分子構造を知ることができ、化合物の定性・定量ができる手法です。そのため、ルーチン測定から研究開発まで幅広く利用されています。
本セミナーでは、ラマン分光法の原理や特徴を解説しつつ、質の高いスペクトルを得るためのノウハウやデータ解析方法を説明します。また、定性・定量・結晶性評価・配向性評価・応力測定等、一般的な測定から応用的な測定まで具体的な測定事例を紹介します。加えて、相補的な情報が得られることから複合分析にも多く使用される赤外分光法との違いや複合分析事例についても解説します。
本セミナーを聴講することにより、ラマン分光法に関する総合的な理解を深めることができます。
URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/2405106
セミナー名:マテリアルズインフォマティクスのためのデータ解析
開催日時:2024年5月31日(金)10:00~17:00
場所:ライブ配信
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:技術情報協会
概要:近年、化学・産業においてデータが蓄積されつつあり、そのデータを解析する動きが活発になっている。しかし、実験結果、高機能性材料などの開発データ、化学・産業プラントにおいて様々な製品を製造する際のデータなど、蓄積されたデータを十分に活用しきれていない状況も存在する。本セミナーでは、そのような化学・産業データの使い方・解析の仕方を基礎から解説する。情報科学・データサイエンスに基づき、データから種々の材料の機能を予測するモデルを構築したり、構築したモデルを活用することで新たな構造・実験条件・材料・装置を設計したりする方法である。さらに、ケモインフォマティクス・マテリアルズインフォマティクス・プロセスインフォマティクス分野を中心にして豊富な応用事例も紹介する。
URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/42990
半導体系
セミナー名:“半日で習得!”半導体技術の全体像マスター講座
開催日時:2024年5月28日(火)13:00~16:00
場所:ライブ配信
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:企業研究会
概要: このセミナーは、そのような背景のもと、短時間に半導体技術全般を俯瞰でき、最新の技術動向も把握できるように構成されている。セミナーを受講することにより、半導体技術全般を理解し、自らの業務の位置づけの再認識や、半導体産業において包括的な見識のものとマネージメントができるエンジニアを育成することの一助としたい。
URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/42775
セミナー名:半導体パッケージ技術の基礎と課題解決およびFOWLP等の最新技術動向
開催日時:2024年5月29日(水)10:30~16:00
場所:ライブ配信セミナー(Zoom)
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:シーエムシー・リサーチ
概要:パッケージに求められる機能およびパッケージの種類の変遷について解説し、またパッケージの製作プロセスの説明とその課題について解説する。さらに最近のパッケージ動向として SiP/WLP/FOWLP/TSV技術などを例に解説する。
URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/43275
セミナー名:ドライエッチングのメカニズムと最先端技術
開催日時:2024年5月29日(水)13:00~16:00
場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:R&D支援センター
概要:台湾TSMCの熊本工場、北海道のラピダスの設立など半導体製造メーカーの日本進出が進んできていますが、2ナノメートルといった超微細な構造を加工するには、エッチング技術が欠かせません。刃物や研磨では得られない超微細加工を実現するためには原子・分子・イオンを活用したエッチング技術が必要であり、デバイス寸法の縮小に伴い、日進月歩の技術革新が行われています。本セミナーではエッチング技術の基礎・メカニズムの説明からスタートし、現在IntelやTSMC, Samsung, SK Hynixなど最新半導体デバイスを製造しているメーカーが使用している先端エッチング技術までを紹介します。エッチング技術にも多くの課題があり、そのブレークスルー技術についてもご紹介いたします。
URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/2405117
セミナー名:半導体製造におけるシリコンウェーハのクリーン化技術・洗浄技術
開催日時:2024年5月30日(木)10:00~17:00
場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:R&D支援センター
概要:本セミナーは、今までノウハウとして門外不出の内向きの技術領域として扱われてきた、歩留まり向上のための「先端半導体クリーン化技術および洗浄・乾燥技術」について、その基礎から最先端技術までを、実践的な観点から豊富な事例を交えて、初心者にもわかりやすく、かつ具体的に解説します。いままで半導体の参考書ではほとんど語られることの無かった先端半導体製造ラインにおける汚染の実態や防止策・除去手法についても多数の実例写真で紹介します。
URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/240577
セミナー名:車載半導体の最新技術と今後の動向
開催日時:2024年6月3日(月)10:30~16:30
場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:トリケップス
概要:半導体は、自動車、鉄道、航空機、スマートフォン、データセンター等のあらゆる産業の競争力を産み出す打ち出の小槌である。また最近では、国家の経済安全保障の「戦略物資」と考えられている。
自動車産業のみならず、IT、通信、電機、鉄道、航空宇宙産業などに携わっている方(携わろうとする方)を対象に、自動運転や電気自動車の性能を左右する車載半導体(コンピューター、センサー、パワー半導体)について、基礎原理から最新技術、今後の動向予測までを講義いたします。
URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/tr240512
分野共通
セミナー名:未来を切り拓く鍵: 生成AIとChatGPTのビジネス活用入門
開催日時:2024年5月28日(火)12:30~16:30
場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:R&D支援センター
概要:この講演では、ChatGPTの基本的な操作は経験しているが、実業務での応用はこれからというエンジニアや事務職の方々に向け、生成AIがビジネスにもたらす革新的な影響について、具体的な体験を通じて深く理解していただきます。ChatGPTをはじめとする生成AIのビジネスシーンでの活用法を探り、知的生産性の向上と競争優位性の確保への道筋を明らかにします。実際の成功事例と失敗事例を参考にしながら、生成AIを効果的に使いこなすための実践的なスキルを身につけていただきます。
URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/2405125
セミナー名:欧州の新機械規則の概要と、機械関連メーカーが求められる対応
開催日時:2024年5月31日(金)13:00~16:00
場所:オンラインセミナー(Zoom)
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:情報機構
概要:2023年7月19日に、欧州新機械規則(EU)2023/1230が施行されました。その結果、機械指令から機械規則への移行期間に入っています。(尚、2027年1月20日には、機械指令は無効となります。)
従って、機械を輸出しているメーカー、また新規に輸出を予定している機械メーカー様は、この新機械規則への準備、および対応が急がれます。本セミナーでは新機械規則(EU)2023/1230の全般と対応について解説いたします。
URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/43234