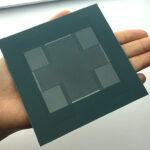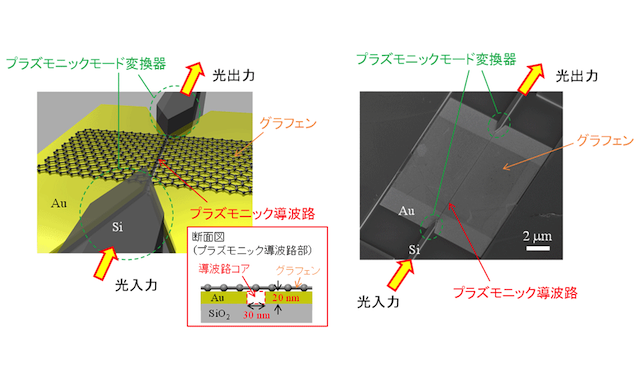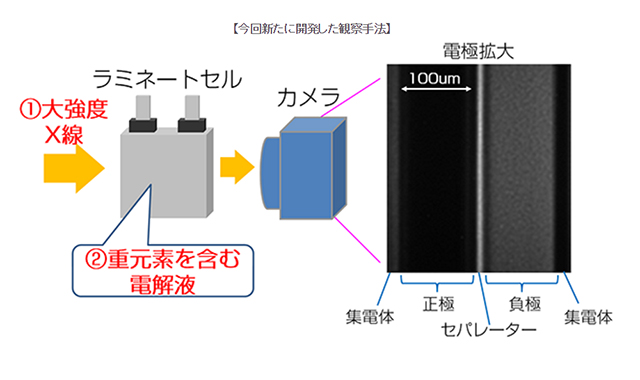- 2024-6-17
- REPORT, 制御・IT系, 化学・素材系, 機械系, 電気・電子系
- AI, EV, NMR, Python, めっき, ものづくり, アルカリ水電解, アンモニア, エポキシ樹脂, エンジニア, キャリア, キャリア形成, ゴム, シランカップリング剤, セミナー, ゼオライト, パワーデバイス, フッ化物系固体電解質, ペロブスカイト太陽電池, マイクロ波加熱, ミリ波, ミリ波材料, 全固体リチウムイオン電池, 全固体電池, 半導体, 半導体パッケージ, 原子間力顕微鏡, 多孔性材料, 展示会, 機械学習, 水素, 水電解, 熱分析, 燃料電池, 画像認識, 研磨加工, 積層セラミックスコンデンサ, 粘着剤, 見本市, 軸受, 透明樹脂, 金属3Dプリンタ, 金属有機構造体, 金属粉末射出成形, 高分子材料

エンジニアの皆さんのお仕事、キャリア形成に役立つ、展示会・見本市、セミナー情報を毎週お届けします。
※掲載している展示会・見本市、セミナーの情報は、6月17日時点のものとなります。申し込み状況は各サイトにてご確認頂けますようお願い致します。
目次
展示会情報(会場別)
セミナー情報
<機械系>
- 開発・設計・生産技術段階での試作品の適切な評価方法
- セラミック玉軸受の優位性の実験的評価と懸念事項
- 研磨加工の基礎と高精度化
- ゴム・高分子材料のトライボロジー特性と接触面の観察および評価方法
- AFM(原子間力顕微鏡)の基礎と最適化・応用・トラブル対策
- 金属粉末射出成形(MIM)の基礎と製品設計のポイント・最新技術動向および金属3Dプリンタとの共進化
<電気・電子系>
- 高分子絶縁材料の劣化メカニズムと部分放電計測ならびに寿命評価
- 徹底解説 パワーデバイス ~Si・SiC・GaN・Ga2O3パワーデバイスの優位性と課題~
- 積層セラミックスコンデンサ(MLCC)における材料、多層化、大容量化、高信頼性化の最新動向
- ミリ波の基礎知識とミリ波材料の評価方法
- フッ化物系固体電解質を用いた全固体リチウムイオン電池の開発動向
- ペロブスカイト太陽電池の基礎・研究と実用化の最新動向からタンデム化による高効率化および今後の展望
- アルカリ水電解の原理・特徴から研究開発動向、今後の展望まで
- 全固体電池材料の最新動向
<制御・ソフト系>
<化学系>
- NMRの基礎講座
- よくわかる!めっき技術/新めっき技術と半導体・エレクトロニクスデバイスへの応用・最新動向
- 熱分析入門
- エポキシ樹脂の耐熱性向上と機能性両立への分子デザイン設計および用途展開における最新動向~最近注目の低誘電率化も解説~
- よくわかる!ゼオライトの基礎、合成および後処理法・物性評価
- 粘着剤の基礎知識と評価法
- 柔らかい多孔性材料最新動向
- マイクロ波加熱の基礎 ~ 電子レンジから高温加熱炉まで ~
- 金属有機構造体(MOF)の基礎と応用・最新動向
- 光学用透明樹脂の基礎と光学特性制御および高機能化
- シランカップリング剤のメカニズムと使用方法
<半導体系>
<分野共通>
展示会情報
会場名:東京ビッグサイト
イベント名:第36回 ものづくり ワールド [東京]
会期:2024年6月19日(水)~21日(金)10:00~18:00 ※最終日のみ17:00まで
会場:東京ビッグサイト 東ホール/南ホール
入場料:詳細はサイト内でご確認ください。
主催者:RX Japan
概要:IT、DX製品、部品、設備、装置、計測製品などを扱う企業が世界中から出展し、国内外の製造業の設計、開発、製造、生産技術、購買、情報システム部門の方々と活発に商談が行われる展示会です。
製造業の最先端事例が学べるセミナーも見どころの一つです。本展は製品カテゴリーごとに10の展示会で構成されています。
URL:https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp.html
セミナー情報
機械系
セミナー名:開発・設計・生産技術段階での試作品の適切な評価方法
開催日時:2024年6月18日(火)10:00~16:00
場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:R&D支援センター
概要:得られたデータから現状の商品と比較して“ばらつき”が改善されたのか、“平均値”が変化したかどうかの評価ができる。市場に出荷されてからクレームが発生しないように、どのような評価をすべきかが解る。試作段階で適切に評価できていない具体的な評価方法を演習で取りあげて、適切でない理由を考える演習を行い、適切な試作品の評価する方法を習得する。
URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/2406116
セミナー名:セラミック玉軸受の優位性の実験的評価と懸念事項
開催日時:2024年6月18日(火)12:30~16:30
場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:R&D支援センター
概要:転がり軸受は、日本人の食生活に例えて“機械の米”と呼ばれることもあり、機械システムを構成する上で欠くことのできない機械要素です。機械設計においては、転がり軸受を機械の仕様に合わせて選定することが仕事となりますが、基礎的な条項をしっかり理解していないと、大きなミスにつながります。
最近では、インバーターによるモータの回転速度制御が普及するにつれて、家電品でも電食が見られるようになりました。これまでに転がり軸受の電食に特化したセミナーを行ってきましたが、その究極的な対策は転動体をセラミック球にすることです。しかし、セラミック球はコストが高いことから普及しませんでした。しかし、自動車のEV化が進み、バッテリー電圧が800Vにも上昇することもあり、セラミック球が注目されてきました。
このセミナーでは、電食対策以外にもセラミック球を用いると転がり軸受として様々な利点(性能向上)があることを実験データに基づいて説明いたします。セラミック玉軸受の使用を検討されている皆様にとって有意義なセミナーにしたいと考えております。
URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/240443
セミナー名:研磨加工の基礎と高精度化
開催日時:2024年6月21日(金)12:30~16:30
場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:R&D支援センター
概要:研磨加工技術は古くからある加工技術にもかかわらず、現在でも多くの先端デバイスの最終仕上げ加工法として用いられています。それは研磨加工が他の加工技術を凌駕する優れた特徴を有するためですが、一方で、検討すべき因子が多く、最適なパフォーマンスを得るのに苦労する方が多いのも実際ではないでしょうか。
この問題を解決し優れた研磨加工を実践するには、研磨加工全般にわたり系統立った知識を適切に獲得し、その知識を駆使する中で最先端の加工技術を習得していく必要があります。
こうした観点にもとづき、本講座では研磨加工の基礎に重点を置きつつ、最新の動向までを整理し系統立って解説します。これから研磨加工に従事されようという初心者・新人の方々、また今一度再確認されたいという方々、さらにはこれからの研磨加工の開発動向を把握されたい加工技術者の方々に有意義な講義になるものと考えます。
URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/240620
セミナー名:ゴム・高分子材料のトライボロジー特性と接触面の観察および評価方法
開催日時:2024年6月21日(金)12:30~16:30
場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:R&D支援センター
概要:タイヤ、シール、ベルト、ワイパー、ゴムローラーをはじめとして、ゴム製品はさまざまなところで使われており、高い摺動性や耐摩耗性を求められています。したがって、ゴム製品を扱うエンジニアは、ゴムの摩擦・摩耗のメカイズムや支配する因子について理解を深め、摩耗の予測や摩耗特性改善などに取組む必要があります。
本講義では、ゴムのトライボロジーを専門とする講師が、その基礎知識をわかりやすく解説します。まず、ゴムのトライボロジーの基礎として、一般的な摩擦の法則と、その適応限界としてのゴム材料への応用を説明します。次に、ゴムの摩耗でしばしば生ずるパターン摩耗機構を解説し、そのメカニズムについて理解を深めます。また、トライボロジーは主に表面で生ずる現象であり、そのため接触面の観察は重要であるということから、光の干渉法および反射法を利用した真実接触面積の観察法を解説します。
URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/240683
セミナー名:AFM(原子間力顕微鏡)の基礎と最適化・応用・トラブル対策
開催日時:2024年6月21日(金)13:00~16:30
場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:R&D支援センター
概要:本セミナーでは、汎用性の高い大気中および液中測定用のAFMを中心に豊富なデータに基づき解説します。これからAFMの導入を検討される方、初めてAFMを操作される方にも分かりやすく装置の基本原理や操作方法、データの取得や解析方法についてまで解説します。特に、講師の経験に基づいて、AFMを導入および使用するユーザー側の視点に立って、技術ポイントを分かり易く解説します。また、AFMに関する日頃のトラブル対策や技術開発相談にも対応します。
URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/240641
セミナー名:金属粉末射出成形(MIM)の基礎と製品設計のポイント・最新技術動向および金属3Dプリンタとの共進化
開催日時:2024年6月24日(月)10:30~16:30
場所:きゅりあん 5F 第3講習室(東京都品川区東大井5-18-1)
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:サイエンス&テクノロジー
概要:MIMは、金属粉末射出成形と呼ばれる革新技術です。プラスチック射出成形と粉末冶金の技術を融合させ、従来の加工方法では難しかった複雑形状の部品を高精度・高強度で量産することを可能にします。誕生から50年という比較的新しい技術ですが国際規格も制定され、自動車、医療機器、電子機器など、様々な分野でMIM部品が採用されています。
本講座では、MIMの製造方法から材料、製品設計、国際規格、最新の学会発表データまで、MIMに関するあらゆる知識を体系的に学ぶことができます。さらに、3Dプリンティング技術との融合による未来展望まで網羅し、精密複雑部品製造ビジネスの可能性を探ります。
URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/st240614
電気・電子系
セミナー名:高分子絶縁材料の劣化メカニズムと部分放電計測ならびに寿命評価
開催日時:2024年6月18日(火)10:30~16:30
場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:R&D支援センター
概要:プラスチックやゴムに代表される高分子材料は,使用環境に存在する劣化因子により劣化を生じ、寿命を迎え時には大事故につながることさえある。したがって、高分子材料を有効に使用するためには劣化メカニズムを正しく理解し、適切な劣化対策を施す必要がある。
本講ではまず劣化要因と劣化メカニズム、特に影響の大きい部分放電現象を概説する。続いて、絶縁設計のポイントならびに部分放電検出の最新技術動向を解説する。また、各種ポリマーの弱点を中心にポリマー選択の際の注意点や、高分子材料の劣化評価法について実例を交えて解説する。さらには、寿命予測の基本的な考え方やポイントを解説し、予測された寿命の正しい解釈について説明する。
URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/240685
セミナー名:徹底解説 パワーデバイス ~Si・SiC・GaN・Ga2O3パワーデバイスの優位性と課題~
開催日時:2024年6月19日(水)10:30~16:30
場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:サイエンス&テクノロジー
概要:パワーエレクトロニクス産業を根底から支えているパワーデバイスは、当面はSiデバイスが主流で製造されるのは間違いありません。一方で、Siデバイスの性能向上に限界が見え始めており、次世代パワーデバイス用材料として、ワイドギャップ半導体が期待されています。SiC、GaNおよびGa2O3は、物性値自身がパワーデバイスに適しており、試作されたデバイスの特性は良好です。しかしながら、結晶製造が難しく高価で品質が劣る、信頼性に不安がある、歩留まりが低い等々、量産化には多くの課題があります。また、これまで日本はパワーデバイス産業を牽引してきましたが、その地位は徐々に落ちてきています。
本セミナーでは、Siおよびワイドギャップ半導体パワーデバイスの進化の歴史と課題および将来展望について、分かりやすく、かつ詳細に解説します。さらに、日本のパワーデバイス産業の復権に向けた提案を述べます。
URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/st240606
セミナー名:積層セラミックスコンデンサ(MLCC)における材料、多層化、大容量化、高信頼性化の最新動向
開催日時:2024年6月19日(水)10:30~16:30
場所:2024年6月19日(水)10:30~16:30
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:情報機構
概要: 当講座ではNi内電MLCCの”材料から始まって、これらの高積層技術、高信頼性技術” と更に将来展望まで幅広く、かつ詳細に解説を行なう。
URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/43657
セミナー名:ミリ波の基礎知識とミリ波材料の評価方法
開催日時:2024年6月19日(水)10:30~16:30
場所:Live配信(Zoom)
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:サイエンス&テクノロジー
概要:2030年頃の実用化に向けて、より高性能な第6世代移動体通信(Beyond 5G/6G)やレベル5搭載完全自動運転車などの研究開発が盛んに行われています。これら次世代システムにおいて、周波数30GHz以上のミリ波と呼ばれる電磁波が注目を浴びています。一方で、ミリ波帯は、数GHzのマイクロ波帯よりも数倍から数十倍以上も周波数が高くなるため、回路材料となる導体や誘電体に起因した損失が増加し、回路実現を困難にします。このため、使用する周波数帯域において精度良く材料評価し、ミリ波システム設計者が望むミリ波材料をいち早く提供できることが求められております。
本セミナーでは、ミリ波の特長やミリ波回路設計などの基礎知識から回路開発に必須となるミリ波材料の評価方法などに関して解説します。
URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/43931
セミナー名:フッ化物系固体電解質を用いた全固体リチウムイオン電池の開発動向
開催日時:2024年6月21日(金)13:00~15:00
場所:ライブ配信(Zoom)
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:新社会システム総合研究所
概要:講演者は、大気安定であり電気化学的安定性が高いフッ化物系固体電解質Li3AlF6を用いて、全固体Li電池を開発している。過去にLi3AlF6のLi+伝導度は、300℃において10-5 S/cm台であると報告されている。講演者は、Li3AlF6はLiClやLi2SO4をボールミリングにより添加することで、室温において10-6 S/cm程度までLi+伝導度が向上し、全固体電池が安定に充放電できることを報告した。またLi2SiF6と固溶体を形成することで、更にLi+伝導度が向上することがわかった。
講演ではLi3AlF6系のLi+伝導特性の詳細や、Li3AlF6-Li2SiF6を用いた全固体Li電池の充放電特性を発表する。また充放電後の負極界面の微細組織観察結果から、現状考えられる充放電サイクル劣化の要因を検討する。
URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/44480
セミナー名:ペロブスカイト太陽電池の基礎・研究と実用化の最新動向からタンデム化による高効率化および今後の展望
開催日時:2024年6月21日(金)13:00~16:00
場所:ライブ配信
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:AndTech (&Tech)
概要: 次世代太陽光発電として最近非常に注目されているペロブスカイト太陽電池の基礎、最新動向からタンデム化による高効率化までを分かりやすく解説します。
URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/44890
セミナー名:アルカリ水電解の原理・特徴から研究開発動向、今後の展望まで
開催日時:2024年6月24日(月)13:00~16:30
場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:サイエンス&テクノロジー
概要:再生可能エネルギー由来の電気を用いた水電解は二酸化炭素を排出しない水素製造技術であり、中でもアルカリ水電解は20世紀初頭から工業的に稼働している。本セミナーでは、水電解の原理を基礎的な熱力学、電気化学を交えて解説し、その後アルカリ水電解の特徴や課題、国内外の動向について紹介する。また要素技術の中で重要となるアノード触媒にフォーカスし、複合酸化物触媒に関する我々の最新成果も織り交ぜながら開発動向を解説する。
URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/st240613
セミナー名:全固体電池材料の最新動向
開催日時:2024年6月24日(月)13:30~15:10
場所:Webセミナー(Zoom)
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:S&T出版
概要:全固体電池は、安全、長寿命、高エネルギー密度、高出力を特長とした次世代二次電池として期待されています。本セミナーでは、リチウムイオン電池、全固体電池の主要材料である固体電解質、硫化物系固体電解質を用いた全固体電池を中心に概説します。次世代全固体電池用材料研究の最新動向についても、講師の研究例を中心に概説します。
URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/43811
制御・ソフト系
セミナー名:機械学習を用いた画像認識技術の基礎とその応用
開催日時:2024年6月19日(水)10:30~16:30
場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:R&D支援センター
概要:近年、多彩なアプリケーションに必要な技術として実用化が進んでいる画像認識技術に関して、カメラによる画像の撮影から、機械学習技術やディープラーニングの活用まで基礎から説明致します。具体的には、光学系を用いた画像の撮影に関する技術から、画像認識技術の概要、一般的な画像認識処理フロー、評価方法、ディープラーニングの基礎、様々な画像認識アルゴリズム、また外観検査などへの応用に関して解説致します。画像認識技術について知りたい方に幅広くおすすめ致します。いくつか講座後出来る演習も準備致します。サブテキストに「トコトンやさしい画像認識の本」を使用します。サブテキストは必須ではありませんが、説明スライドの中にそれぞれの内容に関してサブテキストの対応する項目番号/ページ番号を付加するので、サブテキストの該当箇所を参照いただくことで理解が深まります。
URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/240638
化学系
セミナー名:NMRの基礎講座
開催日時:2024年6月18日(火)13:00~17:00
場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:R&D支援センター
概要:本セミナーではNMRがよく分からない方を対象に、NMRの原理からNMRスペクトルの解釈まで、NMRを感覚的に理解していただくことを目指します。
URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/2406103
セミナー名:よくわかる!めっき技術/新めっき技術と半導体・エレクトロニクスデバイスへの応用・最新動向
開催日時:2024年6月20日(木)10:30~16:30
場所:ライブ配信(Zoom)
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:サイエンス&テクノロジー
概要:1980年代に「めっき技術」の研究が軽視されていったが、1990年代に磁気ヘッドや半導体の銅配線にめっきが使用され、めっき技術への社会的なニーズが高まった。さらに、ウェハ上の薄膜形成がスパッタリング法が中心であったが、1997年のIBMによる銅めっき(ダマシン法)により、半導体にめっき技術が用いられるようになってきた。さらに、厚さが必要な高密度実装でのウエハレベルチップサイズパッケージや部品内蔵基板技術でも、めっき技術が重要なキーテクノロジーとなっている。さらに、有機溶媒からのアルミニウムのめっきなども活発に研究されている。その他の新しいめっき技術の紹介も行う。また、米国や欧州などの産業創生方法についても解説する。
URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/43452
セミナー名:熱分析入門
開催日時:2024年6月21日(金)10:00~16:00
場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:R&D支援センター
概要:熱分析を行ううえで分析の目的に対して的確な情報を得るためには、熱分析の原理や性質を正しく理解し、適切な測定技法を選択するとともに、最適な測定条件で分析し、得られたデータを適確に解釈することが肝要です。
本講では初心者の方々を対象に、熱分析の原理から測定技法の選び方、測定条件の考え方・決め方、測定チャートの見方の基本、装置のメンテナンスまで、熱分析に関する基本的な知識および実践の場で役立つノウハウを平易に解説するとともに、高分子材料を中心に典型的な分析事例を紹介します。
URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/240689
セミナー名:エポキシ樹脂の耐熱性向上と機能性両立への分子デザイン設計および用途展開における最新動向~最近注目の低誘電率化も解説~
開催日時:2024年6月21日(金)10:30~16:30
場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:サイエンス&テクノロジー
概要:基礎編ではエポキシ樹脂の製造方法からその不純物などエポキシ樹脂の基礎から時間をかけて丁寧に解説します。
構造・物性編では主にエポキシ樹脂の分子骨格と物理性状値(軟化点や粘度)、硬化性、耐熱性の関係をデータをもとに解説し、引き続き電気電子材用向けエポキシ樹脂が必要とされる機能を紹介します。
設計・応用編では耐熱性と相反する諸特性を基礎物性理論と硬化物データを関連付けながら解説し、それぞれ相反関係にある機能を両立する分子デザインとその合成技術について紹介します。また最近のトピックスとして低誘電率化の手段として注目されている活性エステル型硬化剤(2022年にエレクトロニクス実装学会より技術賞を受賞)について解説を行います。主に電気電子材料用向けエポキシ樹脂に焦点を当てたセミナーです。
URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/st240609
セミナー名:よくわかる!ゼオライトの基礎、合成および後処理法・物性評価
開催日時:2024年6月21日(金)10:30~16:30
場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:サイエンス&テクノロジー
概要:本セミナーでは「ゼオライトの基礎と合成・応用技術」と題して、ゼオライトの合成および後処理についての基礎知識を学ぶとともに、X線回折、吸着等温線、固体NMRなどによるゼオライトの物性評価の手法についても解説します。ゼオライトは固体触媒ないし触媒担体としての利用が今後も見込まれるので、この用途に注目してゼオライトの結晶構造・組成と物性の関係を学び、触媒特性の向上のための合成法・後処理法についてケーススタディを交えて紹介します。
URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/st240611
セミナー名:粘着剤の基礎知識と評価法
開催日時:2024年6月24日(月)10:00~16:00
場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:R&D支援センター
概要: 本講座では、まず、粘着剤の基礎について簡単に振り返ることからはじめて、その機能発現を理解するために必要となる粘弾性や高分子の特徴的な振る舞いについて説明を進めます。この説明の中で、「なぜ粘着剤は簡単に張り付くのに剥がれにくいのか?」、「なぜ初期のゴム系材料に対してはタッキファイヤーが必須であったか?」等の基本的な疑問に対する物理的な説明を簡単に解説します。最後に、東亞合成が有しているオリゴマー製造技術を軸としたアクリル系粘着材用のタッキファイヤーの設計検討を概観して、開発検討での特性設計の例を用いて話題提供を行います。
URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/2406117
セミナー名:柔らかい多孔性材料最新動向
開催日時:2024年6月24日(月)10:30~16:00
場所:Live配信セミナー(Zoom)
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:技術情報協会
概要:1.グラフェンで作る柔軟なナノポーラス材料、2.柔らかい界面でつくる多孔性MOFナノシー、3.CO2を原料とする金属-有機構造体の合成と評価方法 をテーマとしたセミナー。
URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/44067
セミナー名:マイクロ波加熱の基礎 ~ 電子レンジから高温加熱炉まで ~
開催日時:2024年6月24日(月)10:30~16:30
場所:ライブ配信セミナー(Zoom)
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:シーエムシー・リサーチ
概要:マイクロ波加熱技術の基礎と工学応用について、乾燥・化学合成をベースとして概観する。材料や化学分野の研究者がはじめてマイクロ波加熱を利用するために必要な基礎知識を理解する。マイクロ波プロセスで見られる様々な課題を紹介し、加熱工学・電磁気学の観点から対策法を紹介する。マイクロ波加熱プロセスの実用化へ向けた可能性の判断指標を示すとともに、マイクロ波加熱の生み出す微小領域非平衡効果や学術的に未知とされているマイクロ波効果を紹介する。
URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/44223
セミナー名:金属有機構造体(MOF)の基礎と応用・最新動向
開催日時:2024年6月24日(月)12:30~16:30
場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:R&D支援センター
概要:近年、新しい多孔性素材として注目されている金属有機構造体(Metal-Organic Framework:MOF、多孔性金属錯体または多孔性配位高分子とも呼ばれる)について、その背景や特徴、合成法・評価法といった基礎から最新の研究動向も含めて解説します。具体的には、ガス分離・貯蔵技術への利用、高分子化合物の分離材料としての利用、さらにはMOFを使った新しいナノ材料合成や高分子合成への利用に至るまで、幅広い応用例を取り上げます。レゴブロックのように自在に組み上げることができるMOF合成の実際や、利用に関するエッセンス・ノウハウを知りたいとう方、何から始めたらよいか考えている方にわかりやすくご説明します。
URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/240654
セミナー名:光学用透明樹脂の基礎と光学特性制御および高機能化
開催日時:2024年6月24日(月)13:00~16:30
場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:R&D支援センター
概要:アクリル樹脂(PMMA)、ポリカードネート(PC)や環状ポリオレフィン樹脂(COP、COC)などの透明樹脂はプラスチックレンズ、液晶ディスプレイ、光ディスク、光ファイバーなど包装、光学、光通信分野で広く使われている。また近年、光学機器のデジタル化の急速な進展により、高屈折率、高アッベ数、低複屈折など高い特性をもった高機能な光学用透明樹脂やガラス代替材料としての新規な光学樹脂が数多く開発されている。
本講義では、光学用透明材料やガラス代替樹脂開発のための透明樹脂の概要、分子設計や光学特性の基礎および透明性、耐熱性、屈折率、複屈折率の制御技術など透明樹脂の高機能化について実務に適した内容で分かりやすく解説する。
URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/240448
セミナー名:シランカップリング剤のメカニズムと使用方法
開催日時:2024年6月24日(月)13:00~17:00
場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:R&D支援センター
概要: 本講演では、シランカップリング剤の基本的な使いこなしについて説明する。その他、汎用グレードのシランカップリング剤では性能発現が成し得ない需要に応じるべく、当社で新規に開発したシランカップリング剤を、応用事例を含めて紹介予定である。
URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/240653
半導体系
セミナー名:半導体パッケージの伝熱経路、熱モデルと熱設計・シミュレーション技術
開催日時:2024年6月19日(水)10:30~16:30
場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:R&D支援センター
概要:近年では、機器の電動化が進み、電源回路、モーター駆動回路を中心に、パワー半導体の熱設計が重要になってきている。また、コンピューター性能の向上に加え、スマートフォンやAI、自動運転技術といった新たなアプリケーションニーズから、マイクロプロセッサーの熱管理についても改めて注目が集まっている。本セミナーでは、これらの半導体の熱設計の考え方、3次元シミュレーションを用いる際の注意点や半導体のモデル化に関する動向について解説する。
URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/2406100
セミナー名:パワーデバイス半導体SiC結晶と欠陥評価技術
開催日時:2024年6月20日(木)13:00~16:30
場所:Live配信(Zoom)
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:サイエンス&テクノロジー
概要:SiCパワーデバイスは、N700S系新幹線をはじめとする電鉄車両の電力変換や、電気自動車、などにすでに用いられており、社会実装が始まっている。しかし、無転位の結晶を前提とすることができるSiと比較すると、多くの結晶欠陥がSiCウェハには含まれており、SiCパワーデバイスの生産性を低下させる原因となっている。このため、SiCパワーデバイスにおいては、結晶欠陥の評価が重要となる。
本講座では、SiC結晶やその欠陥の種類、デバイス特性への影響についてレビューした後、結晶欠陥の評価手法に関して解説を行い、SiCウェハの欠陥評価法の理解を深める。
URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/44458
セミナー名:半導体市場の現状と今後の展望2024
開催日時:2024年6月21日(金)13:00~16:00
場所:LIVE配信セミナー(Zoom)
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:R&D支援センター
概要:世界の半導体市場はどこへ向かおうとしているのか、日本政府の半導体産業育成ロードマップはどこまで考えられているのか。日本にはどんな将来が待っているのかを解説。著しい成長・変化に曝されている半導体業界の全体動向や市場動向および今後の成長を学ぶ。
URL:https://www.monodukuri.com/seminars/detail/43528
分野共通
セミナー名:Pythonではじめる機械学習入門講座
開催日時:2024年6月18日(火)10:30~16:30
場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:R&D支援センター
概要:機械学習の入門講座(セミナー)は、巷にたくさんありますが、理論と実践が揃って、はじめて現場で使える技術となります。本セミナーでは、機械学習の理論的側面のみではなく、コンピューターを用いた実践演習を通して、理解を深めていきます。同時に、実践演習では、最近様々な分野で、注目を集めているコンピューター言語Pythonと機械学習系ライブラリ(scikit-learn)を用います。
URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/240274
セミナー名:外観検査自動化に向けた画像処理・AI技術活用の課題と導入のポイント
開催日時:2024年6月19日(水)13:00~17:00
場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:R&D支援センター
概要:本セミナーでは、様々な企業との共同研究や、各種関連学協会での活動の中で学んだ、目視・外観検査の自動化の方法論と実例を紹介する。
URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/2406121
セミナー名:世界中で進むEV、ソフトウエアの進化と新しいモビリティ社会に向け採るべき方策
開催日時:2024年6月20日(木)13:00~15:00
場所:SSK セミナールーム(東京都港区西新橋2-6-2 友泉西新橋ビル4F)
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:新社会システム総合研究所
概要:自動車産業でCASEと呼ばれる100年に1度の大変革が起こっている。それは単に、つながるクルマや自動運転の普及、内燃機関がバッテリーとモーターに変わるクルマの機能や構造の変化だけではない。OTAやSDVによって、全く新しいモビリティライフを提供する。クルマを所有するという概念を変え、販売やアフターサービスの在り方を変え、収益源も変えていく。何よりも、これまでOEMを頂点とした産業構造さえも変えるだろう。
今、世界中で進むEVシフトは、そうした大変革のメインストリームである。EVシフトに出遅れるということは、そうした大きな変化から取り残されることをも意味する。
URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/ssk240606
セミナー名:燃料電池、アンモニア、水素を取り巻く最新動向と今後のビジネス・チャンス
開催日時:2024年6月20日(木)13:00~16:30
場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:S&T出版
概要:2050年には、世界の水素需要は年間6億トンを超えることが見込まれている。家庭用燃料電池、燃料電池車、燃料電池トラック、燃料電池バス、水素ステーション、水素発電、水素エンジン、水素還元製鉄、アンモニア船舶をはじめとした水素とアンモニアを取り巻く最新動向と、欧米諸国、中国の追い上げに負けない、脱炭素時代の経済成長と気候変動対策を見据え、アンモニア・水素社会の2030年に向けての将来動向と最適な日本企業の事業戦略について、資源エネルギーの第一人者が分かりやすく解説する。
URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/stb240602
セミナー名:小規模データに対する機械学習の効果的適用法
開催日時:224年6月24日(月)10:30~16:30
場所:【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。
費用:詳細はサイト内でご確認ください。
主催:R&D支援センター
概要:業務で機械学習、特に深層学習(ディープラーニング)を利用する際、データが少なくて学習できない問題が発生することがあります。例えば、製品の画像による欠陥検査では、正常例は多数集めることができても、欠陥を含む不良品はごく少数しかない場合がほとんどです。また、そもそもデータ取得に大きな人的・時間的コストが必要な場合もあります。このような場合、結局、機械学習や深層学習の利用をあきらめてしまうことがあり、企業の業務へのAI導入を妨げる大きな要因の一つになっています。本セミナーは、そのようにデータが少ない場合でも、有効な学習を行う機械学習の方法を紹介することを目的としています。数式はできるだけ使わず、考え方や原理、要点が分り易い平易な説明を心掛けますので、人工知能や機械学習に対して特に予備知識がない方や、技術職ではない方でも大丈夫です。AIを業務に導入する際の注意点も扱いますし、最後にAIに関する様々な質疑応答やディスカッションを行う「AIよろず相談コーナー」もご用意しましたので、AIにご興味がある方はぜひお気軽にご参加下さい。
URL:https://www.rdsc.co.jp/seminar/240643