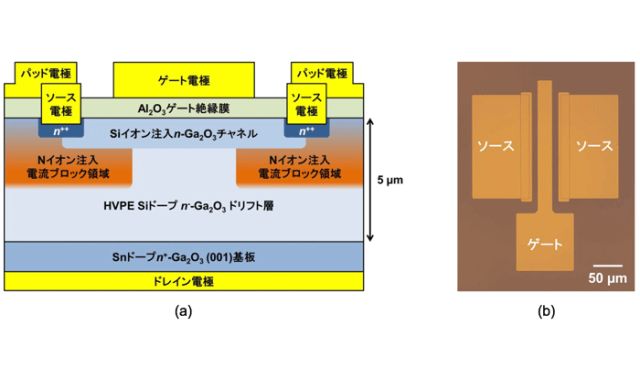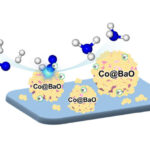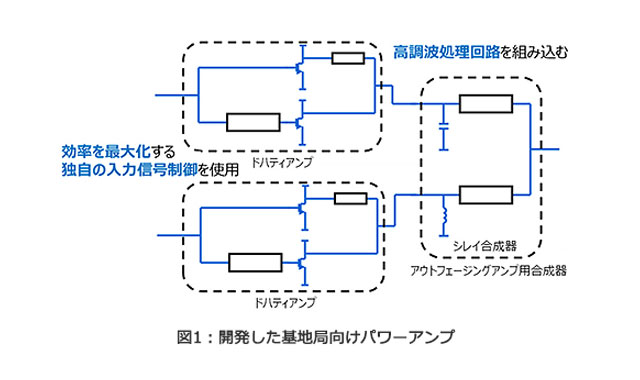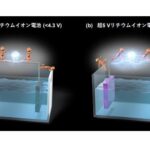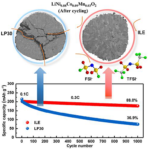- 2025-2-25
- 制御・IT系, 技術ニュース, 海外ニュース
- Nature Physics, アンチモン原子, エラー検知, エラー訂正, シュレーディンガーの猫, シリコンチップ, スピンアップ, スピンダウン, ニューサウスウェールズ大学, 学術, 思考実験, 放射性原子, 核スピン, 量子コンピューター, 量子ビット(キュービット), 量子力学

Photo: UNSW Sydney / Richard Freeman
豪ニューサウスウェールズ大学を中心とした研究チームは、有名な思考実験である「シュレーディンガーの猫」をシリコンチップ内に作り出した。これにより、量子コンピューターのエラー検知とエラー訂正の性能が向上する可能性がある。この研究は2025年1月14日付で『Nature Physics』に掲載された。
「シュレーディンガーの猫」は最も有名な量子力学の思考実験の1つで、猫と毒ガスが入った瓶を一緒に箱の中に入れ、放射性原子が自然崩壊すると瓶が割れるようにした場合の猫の生死を問うものだ。量子力学では、原子が直接観測されない限り、原子は崩壊した状態であると同時に崩壊していない状態にあると考えなければならない。これを「重ね合わせ」状態にあるというが、箱を開けて直接見るまで猫は生と死の重ね合わせ状態にあるという厄介な結論につながる。
一方、量子コンピューターでは、通常、量子情報の基本単位として2つの量子状態だけで記述される「量子ビット(キュービット)」を使う。核スピンを量子ビットとして採用する場合、スピンダウンを「0」の状態、スピンアップを「1」の状態と呼ぶことができる。しかし、スピンの向きが突然変わるとすぐに論理エラーが出てしまう。0が1に、あるいは1が0に一気に変わってしまうため、量子情報は非常にぜい弱であるという問題があった。
それに対し、今回の研究では「猫」としてアンチモン原子を使用した。アンチモンは重い原子で大きな核スピンを持っており、これは磁気双極子が大きいことを意味する。そして、アンチモンのスピンは2方向だけでなく異なる8つの方向をとることができる。
アンチモンのスピンが反対方向を向いている重ね合わせは、単純なダウンとアップの重ね合わせではない。アンチモンの核スピンが完全に下向きの状態と、完全に上向きの状態の2つを重ね合わせると、7つの量子干渉縞が現れるという驚異的な量子状態になる。この干渉縞の数は、ある極端な状態からその真反対の極端な状態に移行するために必要な「スピンの反転」の数に相当する。量子コンピューターでは、これは「0」を「1」に、あるいは「1」を「0」にするために必要な連続エラーの回数に相当する。
つまり、異なる8つのスピンの向きを持つアンチモン原子では、1回のエラーで量子コードが損なわれることはなく、「0」を「1」に変えるには7回連続してエラーが起きる必要がある。情報は依然として「0」か「1」の2進コードでコード化されているが、論理コード間でのエラーの余地が多くあることになる。数回エラーが発生しても情報がすぐに損なわれることがないので、エラーを即座に検知してエラー回数が増える前に修正できる。
今回の研究で、「シュレーディンガーの猫」となるアンチモン原子はシリコン量子チップの中に埋め込まれ、単一原子の量子状態にアクセスできるように作られた。シリコンチップの中に「猫」を入れることでその生死状態、すなわち、原子の量子状態を精巧にコントロールできるようになった。長期的には、現在のコンピューターチップ製造方法と同様の方法を使って、この技術をスケールアップできる可能性があるという。
量子コンピューターの実用化に立ちはだかる最大の障害の1つがエラー訂正だが、量子思考実験の「シュレーディンガーの猫」を現実の世界で実証した今回の研究による発見は、エラー訂正にとって重要な意味を持ち、より安定した新しい方法を量子計算にもたらす。研究チームは、今後、量子コンピューターにおける究極の目標となっている、量子エラー検知とエラー訂正の実証に取り組むとしている。