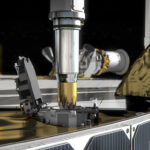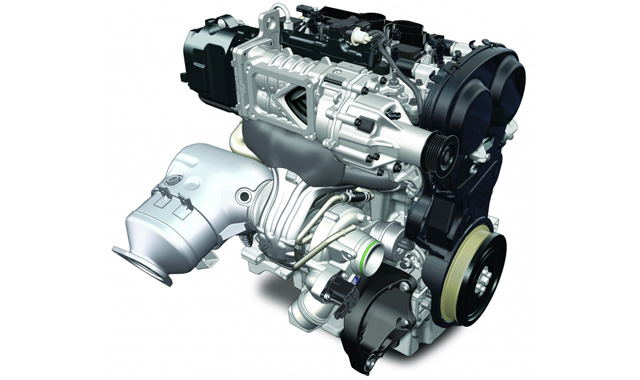- 2025-2-13
- 機械系, 研究・技術紹介
- B 0401-2:2016, JIS, しまりばめ, しめしろ, すきま, すきまばめ, はめあい公差, ピストンリング, メンテナンス, リング溝, 中間ばめ, 位置決めピン, 公差記号, 冷やしばめ, 最大しめしろ, 最大すきま, 最小しめしろ, 最小すきま, 焼きばめ, 誤差, 部品加工

部品を加工する際、図面に15mmと指定されていても寸法通りの加工はできません。なぜなら15mmを狙ったとしても、実際には15.1mmや14.9mmなどの誤差が生じるからです。
ものづくりにおいては、この誤差の許容範囲を適切に設定する必要があり、軸と穴の加工では、それを「はめあい公差」と呼んでいます。
この記事では、はめあい公差の基礎や適用例、公差記号、表の見方、組み合わせなどを解説します。どうぞご覧ください。
はめあい公差とは? 実務で必要な基礎知識
はめあい公差とは、軸と穴の「はめあい」における公差のことです。そもそも公差とは、部品加工などにおいて許容される誤差の最大値と最小値の差を指します。
このはめあい公差を広く設定し過ぎると、軸が大きくて穴が小さ過ぎる場合ははめられなくなり、逆に軸が小さくて穴が大き過ぎる場合は軸として機能しません。だからといって、はめあい公差を厳しく設定し過ぎると、精度を上げるためにコストが高くなってしまうという問題が発生します。
そのため、はめあい公差は機能的に支障がない範囲で、最大限の広さに設定する必要があります。はめあい公差の適切な設定は、ものづくりの実務において必須の要素です。
はめあいの3つの種類と特徴

軸の直径と穴の直径を比べたときに、軸の直径が大きい場合の差を「しめしろ」、穴の直径が大きい場合の差を「すきま」と呼びます。そして、はめあいには「しめしろ」がある「しまりばめ」、「すきま」がある「すきまばめ」、「しめしろ」または「すきま」がある「中間ばめ」の3種類があります。
しまりばめは、軸の最小許容寸法が穴の最大許容寸法より大きいはめあいです。軸が最大許容寸法で穴が最小許容寸法のときに「最大しめしろ」、軸が最小許容寸法で穴が最大許容寸法のときに「最小しめしろ」になります。
すきまばめは、軸の最大許容寸法が穴の最小許容寸法より小さいはめあいです。軸が最小許容寸法で穴が最大許容寸法のときに「最大すきま」、軸が最大許容寸法で穴が最小許容寸法のときに「最小すきま」になります。
中間ばめは、軸の最大許容寸法が穴の最小許容寸法より大きく、かつ軸の最小許容寸法が穴の最大許容寸法より小さいはめあいです。実物の寸法によって、しめしろができる場合とすきまができる場合があります。
しまりばめの特徴と適用例
組み立ての際、軸が穴より大きいしまりばめは圧入します。軸と穴の間に強い摩擦力が生じるため、強固な固定力が得られます。圧入すると簡単に取り外しができないため、軸と穴を一体化させたいときに有効です。
圧入の他に、加熱膨張させた穴に軸をはめる「焼きばめ」や、冷却収縮させた軸を穴にはめる「冷やしばめ」といった組み立て方法もあります。それぞれ常温に戻ったときに穴は収縮し、軸は膨張することで強く固定されます。
しまりばめを歯車と軸の固定に適用すれば、トルクがかかっても空回りせずに動力を確実に伝達できます。また、吸入弁や弁案内の挿入のほか、軸受ブッシュのはめ込み固定などにも使われます。
すきまばめの特徴と適用例
すきまばめは軸が穴より小さいため、手作業で簡単に組み立てられます。軸と穴の間にすきまがあるため、部品を固定することなく滑らかに動かせます。軸を回転させる必要がある軸受部のほか、スライドさせたい摺動部にも適用できます。
メンテナンスで分解しなければならないピストンリングとリング溝や、取り付け取り外しが必要な位置決めピンなどにもすきまばめが使われています。
軸が高温で膨張する場合や、はめあい長さが長い場合などは、機能的に支障が出ない程度にすきまはより大きく設定されます。また、すきまを大きくすることで加工や組み立て、メンテナンスなどを容易にすれば、コスト削減にもつながります。
中間ばめの特徴と適用例
中間ばめは、しまりばめとすきまばめの中間に位置するはめあいです。組み立ての際に、しまりばめほどの強い圧入は必要ありません。ハンマーやハンドプレスなどを使って押し込んだり、潤滑剤を使えば手作業でもはめ込んだりできます。
軸と穴は軽く固定される程度で、部品を損傷させることなく取り外せます。軸に大きなトルクをかけると空回りしてしまうため、回転を防止するにはキーなどを使用します。
精度の高い位置決めをしたい場合や、精密に摺動させたい場合に適しています。強固な固定を必要としない静止部分にも適用可能です。リムとボス、ガバナウエイトとピン、歯車ポンプ軸とケーシング、リーマボルトなどのはめあいで使われます。
公差記号の読み方と実践的な選び方
はめあい公差は「φ15 H7」「φ20 g6」といった形式で表記されます。「φ15」「φ20」は、それぞれ直径15mm、直径20mmを表す基準寸法です。軸や穴はこの基準寸法を狙って加工されます。そして「H7」「g6」が公差記号と呼ばれるものです。アルファベットと数字の組み合わせで、基準寸法に対する公差域(サイズ許容区間)を示します。
アルファベットの大文字は穴、小文字は軸に使われる記号です。穴はA、B、C、CD、D、E、EF、F、FG、G、H、JS、J、K、M、N、P、R、S、T、U、V、X、Y、Z、ZA、ZB、ZCのアルファベット28種類で表されます。Hを基準としてAに向かうほどプラスの公差域、ZCに向かうほどマイナスの公差域です。軸は穴と同じアルファベットの小文字a~zcの28種類で表されますが、hを基準としてaに向かうほどマイナスの公差域、zcに向かうほどプラスの公差域で穴とは逆になっています。
アルファベットに続く数字は「基本サイズ公差等級」の等級番号です。基本サイズ公差等級はIT01、IT0、IT1~IT18の20段階で公差の大小を表します。IT01からIT18に向かって公差の幅は広くなるため、精度が求められる部品ほど数字は小さくなります。
実際の公差は、日本産業規格(JIS)の表で調べられます。また、はめあいの組み合わせは多数ありますが、実践的にはJISで推奨される組み合わせから選ぶと良いでしょう。
はめあい公差表の実践的な活用法
JISの「B 0401-2:2016」に「穴及び軸に対する許容差の表」が記載されています。以下の表は一部を抜粋して編集したものです。
| 図示サイズ (mm) | G | H | JS | K | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||
| 超 | 以下 | 寸法許容差(μm) | |||||||||||||
| – | 3 | +8 +2 |
+12 +2 |
+6 0 |
+10 0 |
±3 | ±5 | 0 −6 |
0 −10 |
||||||
| 3 | 6 | +12 +4 |
+16 +4 |
+8 0 |
+12 0 |
±4 | ±6 | +2 −6 |
+3 −9 |
||||||
| 6 | 10 | +14 +5 |
+20 +5 |
+9 0 |
+15 0 |
±4.5 | ±7.5 | +2 −7 |
+5 −10 |
||||||
| 10 | 18 | +17 +6 |
+24 +6 |
+11 0 |
+18 0 |
±5.5 | ±9 | +2 −9 |
+6 −12 |
||||||
| 18 | 30 | +20 +7 |
+28 +7 |
+13 0 |
+21 0 |
±6.5 | ±10.5 | +2 −11 |
+6 −15 |
||||||
スクロールできます→
この表は「穴に対する許容差」を抜粋したものなので、上部のアルファベットはG、H、JS、Kと大文字になっています。アルファベットの下にある数字6と7は、基本サイズ公差等級の等級番号です。左端の図示サイズは、基準寸法の範囲を示します。
例えば、はめあい公差が「φ15 H7」と表記されていたら、「10mm~18mm」と「H7」が交わる「0μm~+18μm」が実際の公差です。これにより、穴の大きさの許容範囲は「15.000mm~15.018mm」ということがわかります。
よく使用される公差記号の組み合わせ
JISの「B 0401-1:2016」では、「はめあいを決定するための実用的な推奨基準」を定めています。はめあいは以下の組み合わせが多く使われていますが、その中でも経済的な面を考慮して、赤文字の組み合わせが推奨されています。
【推奨する穴基準はめあい方式でのはめあい状態】
| 穴基準 | 軸公差クラス | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すきまばめ | 中間ばめ | しまりばめ | ||||||||||||||||
| H6 | g5 | h5 | js5 | k5 | m5 | n5 | p5 | |||||||||||
| H7 | f6 | g6 | h6 | js6 | k6 | m6 | n6 | p6 | r6 | s6 | t6 | u6 | x6 | |||||
| H8 | e7 | f7 | h7 | js7 | k7 | m7 | s7 | u7 | ||||||||||
| d8 | e8 | f8 | h8 | |||||||||||||||
| H9 | d8 | e8 | f8 | h8 | ||||||||||||||
| H10 | b9 | c9 | d9 | e9 | h9 | |||||||||||||
| H11 | b11 | c11 | d10 | h10 | ||||||||||||||
スクロールできます→
【推奨する軸基準はめあい方式でのはめあい状態】
| 軸基準 | 穴公差クラス | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すきまばめ | 中間ばめ | しまりばめ | ||||||||||||||||
| h5 | G6 | H6 | JS6 | K6 | M6 | N6 | P6 | |||||||||||
| h6 | F7 | G7 | H7 | JS7 | K7 | M7 | N7 | P7 | R7 | S7 | T7 | U7 | X7 | |||||
| h7 | E8 | F8 | H8 | |||||||||||||||
| h8 | D9 | E9 | F9 | H9 | ||||||||||||||
| h9 | E8 | F8 | H8 | |||||||||||||||
| D9 | E9 | F9 | H9 | |||||||||||||||
| B11 | C10 | D10 | H10 | |||||||||||||||
スクロールできます→
穴基準と軸基準がありますが、穴加工は軸加工より精度を出しにくいため、一般的に穴基準が多く使われています。標準的な工具で開けた穴を基準とし、軸を精度高く加工した方が効率的です。
そして、その穴基準の中でも非常によく使われているのが「H7」です。H7は加工のしやすさと精度の高さをバランス良く兼ね備えています。そのため汎用性があり、世界的にも多くの標準部品がH7のはめあい公差で作られています。
まとめ
はめあい公差の基礎や適用例、公差記号、表の見方、組み合わせなどを解説しました。はめあい公差を適切に設定することで、コストを抑えながら機能的に支障のない部品を作れます。
はめあいには、軸を強固に固定する「しまりばめ」、回転や摺動が可能な「すきまばめ」、取り外せる程度に軽く固定する「中間ばめ」の3種類があります。
はめあいの組み合わせは多数ありますが、実践的にはJISで推奨される組み合わせから選ぶと良いでしょう。その中でも「H7」は汎用性が高く、世界中で使われています。
関連記事

ライタープロフィール
fabcross for エンジニア 編集部
現役エンジニアやエンジニアを目指す学生の皆さんに向けて、日々の業務やキャリア形成に役立つ情報をお届けします。